歴史には正史というものが有ります。正史とは正しい歴史の意味であり、国家あるいは日本歴史学会に認められた、いわゆる教科書に載っている歴史のことです。しかし、それがすべて真実であると言うわけではありません。ごく最近起こった事件でさえその真相は闇の中にある場合も有ります。
少し前まで、古代の山陰地方には、記紀神話の中に描かれているような王権は存在しなかったと考えられていました。出雲王国などというものはあくまでも神話の世界の話で、当地にその様な文明・文化は存在しなかったというのが歴史学会の認識でした。
しかし、1984年(昭和59年)、荒神谷遺跡の発掘が、この概念を大きく一変させてしまうことになります。 それに続き、続々と歴史的な考古学的発掘が為されました。
1984 荒神谷遺跡発掘 (島根県簸川郡斐川町神庭西谷) 1996 加茂・岩倉遺跡発掘(島根県雲南市加茂町岩倉)
1991 上淀廃寺発掘 (鳥取県米子市淀江町) 1998 青谷上寺地遺跡発掘調査開始(鳥取県県青谷町)
1995 妻木晩田遺跡発掘 (鳥取県米子市淀江町) 2000 出雲大社御柱発見(島根県出雲市大社町)
これらの発掘によって、古代の山陰地方は神話の故郷から、歴史の故郷へと変貌することになります。
同時に、古代山陰地方における米子(西伯耆)という地の重要性を認識すべき時が来たとも考えられます。
「出雲の源泉であったかもしれない西伯耆を識らずして、出雲は語れず」、と言うべきかもしれません。
歴史は勝者の歴史であるとよく言われます。 しかし、最近の考古学的発見や科学技術の発達は、今まで謎とされてきた多くのものを解明するようになりました。
これらに基づく知見と最近の文献解釈などを併せて、紀元前後頃から、記紀が完成し、山陰が歴史から消え去る794年頃までの米子の古代史、山陰の古代史を、「科学的手法」というものを拠り所として考えて行きたいと思います。
最後に、推論過程ではなく、得られた結論が「ファンタジー」であることを目指しているものだと付け加えさせて頂きます。
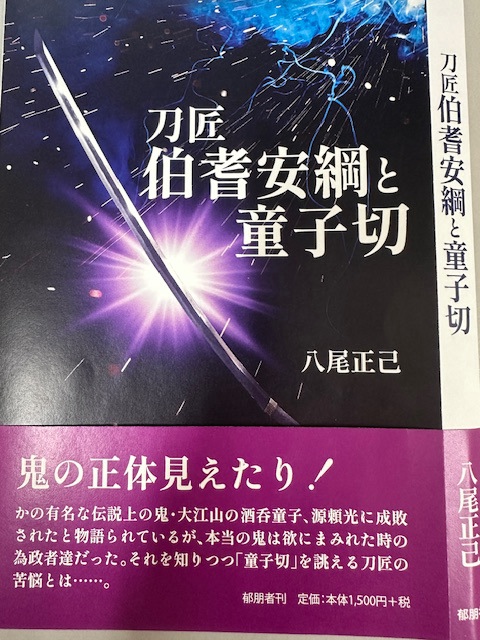
2009−3−7 |