| 播磨国の神社 |
| 播磨国一宮 伊和神社 |
|
所在地
社格
式内社(名神大) 長門国一宮 官幣中社 別表神社
祭神
主祭神=
配祠=
歴史
補足
|
| 播磨国二宮 荒田神社 |
|
所在地
社格
式内社(名神大) 長門国一宮 官幣中社 別表神社
祭神
主祭神=
配祠=
歴史
補足
|
| 播磨国三宮 住吉神社 |
|
所在地
兵庫県加西市北条町北条1318
社格
式内社(名神大) 県社
祭神
主祭神=酒見神、底筒男命、中筒男命、表筒男命、神功皇后
配祠=
歴史
黒駒村で創建され、養老元年(717年)に現在地に遷し奉られた。
大阪の住吉大社らに伝わる「住吉大社神代記」〔天平3年(731年)〕に記された住吉大神の宮九箇処の一社である。
古くは酒見大明神と呼ばれており、明治時代に県社に列格された際に現在の神社名に改められた。
補足
別名:住吉酒見社、住吉酒見神社
|
| 播磨国四宮 白国神社 |
|
所在地
社格
式内社(名神大) 長門国一宮 官幣中社 別表神社
祭神
主祭神殿=
配祠=
歴史
補足
|
| 播磨国五宮 高岳神社 |
|
所在地
社格
式内社(名神大) 播磨国四宮 官幣中社 別表神社
祭神
主祭神=
配祠=
歴史
補足
|
| 播磨国総社 射楯兵主神社 |
|
所在地
兵庫県姫路市総社本町190
社格
式内社(名神大) 播磨国五宮 官幣中社 別表神社
祭神
主祭神=射楯大神(五十猛尊)、兵主大神(大国主命)
配祠=
歴史
補足
|
| 生田神社 |
|
所在地
兵庫県神戸市中央区下山手通1丁目2-1
社格
式内社(名神大) 播磨国五宮 官幣中社 別表神社
祭神
主祭神=
配祠=
歴史
創建 神功皇后元年(201年)
当初は、現在の新神戸駅の奥にある布引山(砂山(いさごやま))に祀られていた。
799年(延暦18年)4月9日の大洪水により砂山の麓が崩れ、山全体が崩壊するおそれがあったため、村人の刀祢七太夫が祠から御神体を持ち帰り、その8日後に現在地にある生田の森に移転したといわれている。
平城天皇の806年(大同元年)には「生田の神封四十四戸」と古書には記され、現在の神戸市中央区の一帯が社領であった所から、神地神戸(かんべ)の神戸(かんべ)がこの地の呼称となり中世には紺戸(こんべ)、近年に神戸(こうべ)と呼ばれるようになった。
補足
稚日女尊(わかひるめのみこと)である。「稚く瑞々しい日の女神」を意味し、天照大神の幼名とも妹とも和魂であるとも言われる。
|
|
生田裔神八社(いくたえいしんはちしゃ)
生田神社を囲むように点在している裔神八社のこと。
近年は港神戸守護神 厄除八社(みなとこうべしゅごしん やくよけはちしゃ)とも呼ばれ、数字の順に巡ることを八宮巡りといい、厄除けになるとされている。
一宮神社
所在地 : 兵庫県神戸市中央区山本通1丁目
祭神 : 田心姫命
二宮神社
所在地 : 神戸市中央区二宮町3丁目
祭神 : 天忍穂耳尊 ・応神天皇
三宮神社
所在地 : 神戸市中央区三宮町2丁目
祭神 : 湍津姫命
幕末に、この神社の前で神戸事件が起こった。境内に「神戸事件発生地の碑」が建てられている。
四宮神社
所在地 : 神戸市中央区中山手通5丁目
祭神 : 市杵島姫命
五宮神社
所在地 : 神戸市兵庫区五宮町
祭神 : 天穂日命
明治時代、湊川神社の氏子社になりかけたが、生田神社社家先祖である海上五十狭茅の子孫の家が近隣にあった為、住民の申し出により、取り止めとなった。
現在は、8社中一番標高の高い場所に鎮座しており、元は宇治川の氾濫原にあったため、現在地に移ったのではとの説がある。
六宮神社
所在地 : 神戸市中央区楠町3丁目 八宮神社の境内(明治初期に道路拡張のため八宮神社に合祀)
祭神 : 天津彦根命・応神天皇
七宮神社
所在地 : 神戸市兵庫区七宮町2丁目
祭神 : 大己貴尊・天児屋根命
生田神社とは関係が無い長田神社の末社ともされ、前身はみぬ売神社とされている。
元々は会下山南麓で、北風家が祀っていたといわれている。
八宮神社
所在地 : 神戸市中央区楠町3丁目
祭神 : 熊野杼樟日命・素盞鳴尊
|
| 海神社(わたつみじんじゃ) |
|
所在地
社格
式内社(名神大)
祭神
主祭神殿=
配祠=
歴史
補足
|
| 安芸国の神社 |
| 安芸国一宮 厳島神社(いつくしまじんじゃ) |
|
所在地
広島県廿日市市宮島町1-1
社格等
式内社(名神大)、安芸国一宮、官幣中社、別表神社
祭神
主祭神=市杵島姫命、田心姫命、湍津姫命
歴史
宮島は、古代より島そのものが神として信仰の対象とされてきたとされている。
推古天皇元年(593年)、土地の有力豪族であった佐伯鞍職が社殿造営の神託を受け、勅許を得て御笠浜に社殿を創建したのに始まると伝わる。
文献での初出は弘仁2年(811年)で、延喜式神名帳では「安芸国佐伯郡 伊都伎嶋神社」と記載され、名神大社に列している。
平安時代末期に平家一族の崇敬を受け、仁安3年(1168年)ごろに平清盛が現在の社殿を造営した。
平家一門の隆盛とともに当社も盛えた。
平家の守り神であった。
平家滅亡後も源氏をはじめとして時の権力者の崇敬を受けた。
戦国時代に入り世の中が不安定になると社勢が徐々に衰退するが、毛利元就が弘治元年(1555年)の厳島の戦いで勝利を収め、厳島を含む一帯を支配下に置き、当社を崇敬するようになってから再び隆盛した。
元就は大掛かりな社殿修復を行っている。
豊臣秀吉も九州遠征の途上で当社に参り、大経堂を建立している。
補足
日本全国に約500社ある厳島神社の総本社である。
|
| 周防国の神社 |
| 周防国一宮 玉祖神社(たまのおやじんじゃ) |
|
所在地
山口県防府市大字大崎1690
社格
式内社(名神大) 国幣中社 別表神社
神階=従一位
祭神
主祭神=玉祖命
他一座未詳 (岩戸隠れの際に八咫鏡を作った石凝姥命(いしこりどめ)とする説などがある)
歴史
社伝によれば、玉祖命がこの地で亡くなったため、社殿を造営して祀ったのに始まるとされ、附近には玉祖命の墳墓と伝えられる「玉の石屋」がある。
平安時代には周防国一宮として崇敬を受け、中世以降も歴代領主から崇敬された。
補足
玉祖命・石凝姥命ともに日本神話では岩戸隠れの段に初出し、天孫降臨の段では五伴緒として天孫とともに天降った。
|
| 長門国の神社 |
| 長門国一宮 住吉神社 |
|
所在地
山口県下関市一の宮住吉1-22-1
社格
式内社(名神大) 長門国一宮 官幣中社 別表神社
祭神
第一殿=住吉三神 第二殿=応神天皇 第三殿=武内宿彌命
第四殿=神功皇后 第五殿=建御名方命
歴史
『日本書紀』神功皇后紀によれば、三韓征伐の際、新羅に向う神功皇后に住吉三神(住吉大神)が神託してその渡海を守護し、帰途、大神が「我が荒魂を穴門(長門)の山田邑に祀れ」と再び神託があり、穴門直践立(あなとのあたえほんだち)を神主の長として、その場所に祠を建てたのを起源とする。
創建の由緒から軍事と海上交通の神として厚い崇敬を受け、延喜式神名帳では名神大社に列し、長門国一宮とされた。
鎌倉時代に入り、源頼朝を始め歴代将軍からの社領などの寄進を受けた。
戦国時代に一時衰微したが、大内氏、毛利氏からの崇敬を受けて復興し、江戸時代には長州藩主毛利氏によって社殿の修復が行われた。
補足
大阪の住吉大社が住吉三神の和魂を祀るのに対し、当社は荒魂を祀る。
|
| 参考資料 |
|
「神社辞典」 (東京堂出版 1997)
Wikipedia 「神社一覧」 |
|
 |
「ファンタジ−米子・山陰の古代史」は、よなごキッズ.COMの姉妹サイトです |
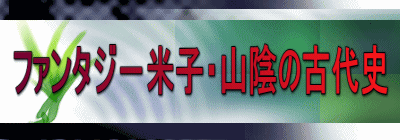  |
|