| 境港市周辺の神社 |
| 日御碕神社 (小篠津) |
|
所在地
鳥取県境港市小篠津町1175番
社格等 郷社
祭神
主祭神=大日霎貴命
合祀=素盞鳴尊、天児屋根命、大土御祖命、倉稲魂命、事代主命、菅原道真公、豊受姫命
歴史:鳥取県神社誌より
創立年月ならざれど、往古より小篠津、新屋、和田、富益四ヶ村の氏神と崇敬奉祀せり。
棟札の最も古きを元亀3年丁申9月修復のものとす、他に沿革など記すべきものなし。
倉稲魂命は本社に稲荷大明神と称し奉祀、素盞鳴命は村内中屋敷に、事代主命は恵美須神社と称へ村内恵比須通り、菅原道真公は天満宮と称へ中屋敷にありて何れも当社の摂社なり。
明治元年神社改正の際合祀せらる、同年郷社に列す。
明治40年2月3日神饌幣帛料供進神社に指定せらる。
大正元年11月18日
中浜村大字小篠津字一尺三寸鎮座無格社三軒屋神社(祭神:素盞鳴尊)
同村大字新屋字榎下鎮座無格社新屋神社(祭神:豊受姫命)を合併す。
補足:鳥取県神社誌より
建造物 本殿、弊殿、拝殿ね神饌所、神楽殿、社務所、神輿庫、随神門
境内坪数=825坪 氏子戸数=1131戸 |
|
| 余子神社 |
|
所在地
鳥取県境港市竹内町1645番
社格等 郷社
祭神
主祭神=第7代孝霊天皇
合祀=稲田姫命、脚摩乳命、手摩乳命、大日孁貴命、素盞鳴命、倉稲魂命
境内神社=蛭子神社、祭神 事代主命
歴史:鳥取県神社誌より
創立年月不詳
明応9年庚申11月再建の棟札によれば、当社は境、上道、中野、福定,竹内、高松の六村の大産土神として崇敬せしが、特に旧藩主より厚く崇敬せら幕提灯等寄附せらる。
明治元年神社改正の際郷社に列す。
現今は境町及び餘子村の産土神として崇敬す。
明治40年2月3日神饌幣帛料供進神社に指定せらる。
大正4年6月17日
境町字宮ノ西鎮座無格社岡畑神社(祭神 素盞鳴命、倉稲魂命)を合併す。
補足:鳥取県神社誌より
例祭日 10月12日
建造物 本殿、幣殿、拝殿、神饌所、社務所、随神門、手水舎
境内坪数 782坪
氏子戸数 2100戸
|
|
| 日御碕神社 (渡) |
|
所在地
鳥取県境港市渡町1487-4
社格等
祭神
歴史:鳥取県神社誌より
補足:鳥取県神社誌より
|
| 幸神神社 |
|
所在地
鳥取県境港市幸神町906番5
社格等
祭神
猿田彦命、宇受売命、事代主命、素盞鳴命、綿津見命
歴史:鳥取県神社誌より
創立年月不詳ならざれども、明和六年の棟札あり。
三寶荒神宮と号せしを明治元年神社改正の際蛭子神社と改称、青木神社へ合祭。
明治12年復旧存置せしが、同42年2月青木神社に蛭子神社を合祀、社号を幸神神社と改称す。
青木神社の創立年月も不詳、唯寛永3年11月修復以後の棟札あるのみ。
補足:鳥取県神社誌より
建造物 本殿、弊殿、拝殿
境内坪数=164坪 崇敬戸数=230戸
|
| 大港神社 |
|
所在地
鳥取県境港市栄町161番
社格等
境、上道、中野、福定,竹内、高松の六ヶ村の産土神
祭神
品田和気尊、大帯姫尊、比咩大神、武内宿禰命、亀井能登守安綱、須佐之男尊、大己貴命、事代主命、清若丸、手島四良三郎、小磯亦四郎
境内神社=北野神社:祭神:菅原道真
歴史:鳥取県神社誌より
創立年月不詳。
棟札は慶安2年10月建立以前の分無きも社宝に永享3年の記文のものあり。
往古より境、上道、中野、福定,竹内、高松の六ヶ村の産土神にして八幡宮と号し、旧藩主よりの崇敬厚く幕提灯等の寄進あり。
明治元年今の社号に改称せられ、郷社餘子神社の摂社となり後年無格社に改められる。
武内宿禰命は以前の末社なり。
亀井能登守安綱は亀井神社と号し元本社の東側に鎮座せられしものなるが、清若丸、手島四良三郎、小磯亦四郎は末社なりしを明治元年境町大字境字宮ノ前鎮座無格社亀井神社に合祭し、大正4年6月17日亀井神社を当社に合併す。
昭和8年2月4日神饌幣帛料供進神社に指定せらる。
補足:鳥取県神社誌より
建造物 本殿、幣殿、拝殿、神饌所、随神門、手水舎
境内坪数=626坪 氏子戸数=1600戸
|
|
西灘神社
|
|
所在地
鳥取県境港市外江町3557番
社格等
祭神
素戔鳴命、稲田姫神、大日霎貴神
歴史:鳥取県神社誌より
創立年月不詳。
元京都祇園社出雲日御崎神社の両社より勧請西灘の地に二社殿を建立奉祀せしが、明治元年神社整理の際合併一社となる。
古来祇園社と称へしを此の時今の社号に改称せらる。
補足:鳥取県神社誌より
建造物 本殿、通殿、拝殿、神輿庫、祭器庫
境内坪数 373坪 氏子戸数 700戸
|
| 廣見神社 |
|
所在地
鳥取県境港市中野町5188
社格等
祭神
布都御魂命
歴史:鳥取県神社誌より
創立年月不詳。
往古より石上明神と号せしを、明治元年今の社号に改められ餘子神社の摂社たり。
補足:鳥取県神社誌より
建造物 本殿、拝殿
境内坪数=76坪 氏子数=300戸
|
| 濱田神社 |
|
所在地
鳥取県境港市竹内町
社格等
祭神
大国主命
歴史:鳥取県神社誌より
往古より社もなく松木を以て地主神と数敬せしを、明治元年神社改正の際濱田神社と改めらる。
補足:鳥取県神社誌より
建造物 社殿なし神木を祀る。
境内坪数=3坪 氏子戸数=280戸
|
| 高松神社 |
|
所在地
鳥取県境港市松町573
社格等
祭神
素盞鳴命
歴史:鳥取県神社誌より
創立年月不詳、寛永二年の棟札あり、その他の沿革詳ならず。
補足:鳥取県神社誌より
建造物 本殿、弊殿、拝殿
境内坪数=153坪 崇敬戸数=120戸
|
| 福定神社 |
|
所在地
鳥取県境港市福定町374番
社格等
祭神
磐長姫命
歴史:鳥取県神社誌より
創立年月不詳、往古より荒神宮と称す。
明治元年神社改正の際福定神社と改められ餘子神社の摂社となる。
補足:鳥取県神社誌より
建造物 本殿、神楽殿
境内坪数=231坪 氏子数=90戸
|
| 上道(あがりみち)神社 |
|
所在地
鳥取県境港市上道町
社格等
村社
当社は上道・境・中野・福定・竹内五か村の氏神であった。
祭神
事代主命、市杵島姫命、大海津美神、武御名方主神
歴史:鳥取県神社誌より
創立年月は不詳。
往古より恵美須神と号し尊敬せしが、明治維新の際今の社号に改めらる、
明治45年3月村社に列す。
大正3年1月6日神饌幣帛料供進神社に指定せらる。
慶安二年(1649)恵美須神社として創られたものといわれる。
明治元年(1868)、近隣小社を合祀し、上道神社と改名された。
補足:鳥取県神社誌より
建造物=本殿、神楽殿
境内坪数=556坪 氏子戸数=350戸
|
| 白尾(しらお)神社 |
|
所在地
鳥取県境港市外江町2068番
社格等
祭神
主祭神=天照大神
合祀=豊受姫神、素戔鳴命、菅原道真、事代主命、市杵島姫命、岩長姫命
歴史:鳥取県神社誌より
創社年代は不明
正応年間(1288?92)に石州津和野の浪士・勝田上総介四郎(五郎とも)という者が当地にやって来て、市内鬼ケ沢に住んで農耕を妨害する悪賊を亡ぼし、土地を開拓して勝田庄を作った。
勝田四郎の死後、地元の人々は、その功績を讃え、勝田明神として新屋村に神社を創り祀ったといわれる。
後に外江の現在地に神社は移されたが、米子城が築城されたとき(天文22年・1553)、城の鬼門鎮護の神として、祭神は再び米子に遷された。
これが現在の勝田神社である。
祭神勝田四郎を失った当社は、その後に伊勢神宮を勧請し、近世になると、「伊勢の宮」と呼ばれていたという。
補足1:鳥取県神社誌より
例祭日 10月21日
建造物 本殿、幣殿、通殿、拝殿、神輿庫二棟、神楽殿、祭器庫
境内坪数=830坪 氏子戸数=700戸
補足2
白尾とはかつての祭神、勝田四郎の名前の転化といわれている。
|
| 参考史料 |
「鳥取県神社誌」 (澤田文精堂 1934)
「日野郡誌」 (名著出版社 1926)
「因伯叢書第4巻伯耆誌」 (名著出版社 1972)
「神社辞典」 (東京堂出版 1997)
Wikipedia 「神社一覧」
|
|
 |
「ファンタジ-米子・山陰の古代史」は、よなごキッズ.COMの姉妹サイトです |
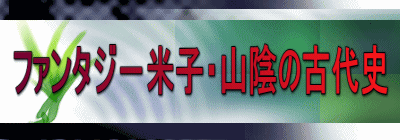  |
|