| 暦法と紀年法 |
|
暦(こよみ、れき)とは
時間の流れを年・月・週・日といった単位に当てはめて数えるように体系付けたもの。
暦法(れきほう)とは
毎年の暦を作成する際の基本的な諸原則のこと。
何を基準として1年を定めるか、閏(閏日・閏月)をどのようにして決めるかなどにより、さまざまな暦法がつくられたが、大別すると以下の3種類がある。
1:太陽暦
2:太陰太陽暦
3:太陰暦
紀年法
年を数えたり、記録する方法をいう。
ある年(紀元)を基準にして年を数えていく紀年法が一般的であるが、干支紀年法やインディクティオンのように周期によって機械的に年を数えていくものもある。
元号と年号
元号
任意の年を紀元と定めて数える紀年数のみを指す
年号
それに付ける漢字名を指すとして区別すること
|
| 暦法の種類 |
| 1:太陽暦 |
|
地球が太陽の周りをまわる周期(太陽年)のみを元にして作られた暦法。
①ユリウス暦
地球が太陽の周りをまわる周期を元にして作られた太陽暦の一種である暦法。
ユリウス・カエサルによって制定され、紀元前45年1月1日より実施された
②グレゴリオ暦
1582年にローマ教皇・グレゴリウス13世がユリウス暦を改良して制定した暦。
現行の太陽暦として世界各国で用いられる。
|
| 2:太陰太陽暦 |
|
太陰暦を基にしつつも閏月を挿入して実際の季節とのずれを補正した暦。
①中国暦
古六暦
顓頊暦-秦・前漢(? - 紀元前104年)
太初暦(三統暦)前漢・新・後漢(紀元前104年 - 84年)
四分暦 - 後漢(85年 - 220年)・魏(220年 - 236年)・呉(222年)・蜀(221年 - 263年)。
乾象暦 - 呉(223年 - 280年)
景初暦
魏・西晋・東晋・劉宋(237年 - 444年)・北魏(398年 - 451年)
元嘉暦 - 劉宋・南斉・梁(445年 - 509年)
大明暦 - 梁・陳(510年 - 589年)
三紀暦 - 後秦(384年 - 517年)
玄始暦 - 北涼(412年 - 439年)・北魏(452年 - 522年)
正光暦
北魏(523年 - 534年)・東魏(535年 - 539年)
西魏(535年 - 556年)・北周(556年 - 565年)
興和暦 -
東魏(540年 - 550年)
天保暦 -
北斉(551年 - 577年)
天和暦 - 北周(566年 - 578年)
大象暦 - 北周(579年 - 581年)・隋(581年 - 583年)
開皇暦 - 隋(584年 - 596年)
大業暦 - 隋(597年 - 618年)
皇極暦
戊寅元暦 - 唐(619年 - 664年)
麟徳暦 - 唐(665年 - 728年)
大衍暦 - 唐(729年 - 761年)
五紀暦 - 唐(762年 - 783年)
正元暦 - 唐(784年 - 806年)
②バビロニア暦
③和暦
日本独自の暦法であり、元号とそれに続く年によって年を表現する。
飛鳥時代の孝徳天皇による大化がその始まりであり、以来15世紀に渡って使われ続けてきている。
現在では、元号法により天皇の皇位を継承する際にのみ改めることが定められている。(一世一元の制)、明治以前では不吉なことがあったり病が流行する度に改元され、そのほとんどは1年から長くて十数年の非常に短い期間しか持続しなかった。
そのため、平成までに250の元号が存在する。
|
| 3:太陰暦 |
|
太陰暦(たいいんれき)とは、朔望月(月の満ち欠けの周期)を1ヶ月とする暦法である。
東アジアで単に太陰暦・陰暦といった場合、太陰太陽暦である中国暦・和暦など意味することが多い。
|
| 日本における暦法 |
| 1:元嘉暦((げんかれき) 推古天皇12年(604年) |
|
中国・南北朝時代の宋の天文学者・何承天が編纂した暦法である。
南朝の宋・済・梁の王朝で、元嘉22年(445年)から天監8年(509年)までの65年間用いられた。
日本には朝鮮半島の百済を通じて6世紀頃に伝えられた。
当初は百済から渡来した暦博士が暦を編纂していたか、百済の暦をそのまま使用していたと考えられる。
推古天皇10年(602年)に百済から学僧・観勒が暦本などを携えて来日し、帰化人系の子弟らにこれらを学習させた。
平安時代の書物『政事要略』には、推古天皇十二年正月朔日に初めて日本人の手によって作られた暦の頒布を行ったとの記述があり、これは元嘉暦によるものであったと考えられる。
|
| 2:儀鳳暦(ぎほうれき) 文武天皇元年(697年) |
|
中国暦の一つで、中国唐の天文学者・李淳風が編纂した太陰太陽暦の暦法である。
中国でのもともとの名は麟徳暦(りんとくれき)である。
定朔法を用いており、優れた暦法とされる。
なお、この暦において初めて進朔が採用された。
儀鳳暦は持統天皇4年(690年)から元嘉暦との並用を始めた(『日本書紀』持統4年11月甲申条)。
ただし、当初は日食計算などに主として用いられ、『日本書紀』の期日も元嘉暦であったされている(文武天皇の即位期日(八月朔日=8月1日)の干支を『日本書紀』は元嘉暦、『続日本紀』は儀鳳暦で表記しているためにあたかも2説あるようにも見えるが、実際には同日であった)。
5年後の文武天皇元年(697年)から儀鳳暦が単独で用いられるようになった(ただし、前年の持統天皇10年説・翌年の文武天皇2年説もある)。
ただし、新暦の特徴の1つであった進朔は行われなかったとされている。その後67年間使用されて、天平宝字8年(764年)に大衍暦に改暦された。
|
| 3:大衍暦(たいえんれき/だいえんれき) 天平宝字8年(764年) |
|
中国・唐の僧・一行(いちぎょう)が玄宗の勅令を受けて編纂した暦法である。
一行らは南は交州から北は鉄勒にいたる子午線測量を行い、中国全土に及ぶ大規模な天文測量を実施した。
中国では、開元17年(729年)から上元2年(761年)まで33年間用いられた。
日本には、吉備真備が天平7年(737年)に唐から持ち帰った。
だが、当時の日本には暦学に通じた人材が不足していた(『続日本紀』天平2年3月辛亥条)ため、実施には慎重な準備が進められた(『続日本紀』天平宝字元年11月癸未条、『類聚三代格』所収同日(11月9日)勅)後に藤原仲麻呂政権下で実現される事になる。
天平宝字8年(764年)から貞観3年(861年)までの98年間用いられた。
天安2年(858年)からの4年間は改暦の準備として五紀暦と併用されたが、貞観4年(862年)に宣明暦が導入された。
|
| 4:五紀暦 |
|
|
| 5:宣明暦 貞観4年(862年) |
|
|
| 6:貞享暦 |
|
|
| 7:宝暦暦 |
|
|
| 8:寛政暦 |
|
|
| 9:天保暦 |
|
|
| 10:グレゴリオ暦 |
|
|
|
|
| 日本における暦の歴史 |
| 中国暦導入以前 |
|
|
| 中国暦導入以後 |
|
欽明14年(553年)
日本書紀
暦博士の任期が切れたので交代の博士を派遣するように百済に使者を送る。
百済は宋の元嘉暦を採用していた。よってこの時の暦法は元嘉暦と考えられる。
欽明15年(554年)
日本書紀
百済より、暦博士固徳王保孫(ことくおうほうそん)ら来日。
推古10年(602年)
日本書紀
百済より観勒(かんろく)という学僧が、暦本、天文地理書、遁甲方術の書をもって、来日。
暦法については玉陳(たまふる)という人物が習う。
推古12年(604年)
暦日を初めて用いる(元嘉暦)。
文武元年(697年)まで使われる。
643(皇極天皇二)年
日本書記
五月十六日、日本最古の月食の記録。
660年
日本における漏剋の初め。
671年
漏剋の使用(時の記念日の制定根拠)
675年
初めて占星台を設置
持統4年(690年)
日本書紀
元嘉暦と儀鳳暦の併用の採用
692年(持統天皇六)年
元嘉暦と儀鳳暦の併用を実行?→元嘉暦と儀鳳暦の併用期間については、諸説あり。
697年(文武天皇元)年
儀鳳暦採用、実施は翌年から。
701(大宝元)年
大宝律令制定。中務省の陰陽寮を置き、造暦にあたらせる。十一月一日に頒暦の儀式を行ったのち、各官庁、地方官庁に配布された。(大宝律令)
729年(唐・開元十七年)
麟徳暦(儀鳳暦)を廃し、僧・一行が編纂した大衍暦を採用。
730(天平二)年
続日本紀
陰陽、医術、七曜(天文学)、頒暦は、国家の要でありながら、これらの指導者は、高齢のため、弟子をとって教授させるように、太政官が聖武天皇に上奏。(日本書紀より)
735(天平七)年
続日本紀
入唐留学生 吉備真備、大衍暦経1巻(大衍暦の理論を記す)、大衍暦立成12巻、太陽の影を測る鉄尺1枚などを持って帰国。
757(天平宝字元)年
暦生の学ぶべき書として、漢書・晋書の律暦志・大衍暦議、九章、六章、周脾、定天論の書をあげる。
758(天平宝字二)年
陰陽寮を大史局と改める。(続日本紀)
764年(天平宝字八)年
続日本紀儀鳳暦を廃し、大衍暦を採用する。
778年
羽栗翼(第十二次遣唐使として唐に渡る)、「宝応五紀暦」を学び帰国。「宝応五紀暦」を採用するように建言するが、「習学する人無く、業を伝うることを得ず」ということで採用見送り。
|
| 参考文献、資料等 |
|
日本書紀 (教育社
ウィキペディア「暦」
|
|
 |
「ファンタジ-米子・山陰の古代史」は、よなごキッズ.COMの姉妹サイトです |
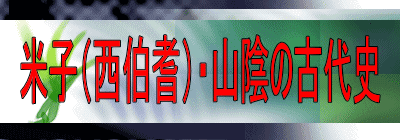  |
|